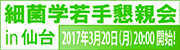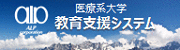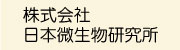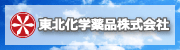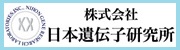ご挨拶
第90回日本細菌学会総会の開催にあたって
この度、第90回日本細菌学会総会を、平成29年3月19日(日)〜21日(火)の3日間の会期で、仙台国際センターにて開催することとなりました。1902年(明治35年)に第1回日本医学会(微生物・寄生虫学・衛生学の連合部会)以来115周年、1927年に北里柴三郎先生が総会長として第1回衛生学微生物学寄生虫学聯合学会(第1回日本細菌学会総会)が開催されて90周年を迎えます。この間、仙台市では、1950年(昭和25年)に黒屋政彦先生(細菌学会黒屋奨学賞として人材育成へのご遺志が継承されています)が第23回日本細菌学会総会を、さらに、1972年(昭和47年)には、石田名香雄先生が第45回総会を開催されています。従いまして、この度の東北・仙台での総会開催は、前回の第45回以来45年目、ほぼ半世紀ぶりに日本細菌学会の歴史上3度目の仙台での開催となり記念すべき総会となりました。また、2011年の東日本大震災から6年目を迎え復興と再生を目指す東北地方での震災後はじめての開催となります。日本細菌学会という日本で最も歴史ある学会の仙台での開催を契機に、東北地方の学術振興が益々加速することを期待しております。
さて、本学会においては、細菌学、真菌学、感染症学、生体防御・免疫学、感染疫学、環境微生物学、ワクチン・抗菌化学療法などの予防・治療医学を中心に、医学系・歯学系・薬学系・農獣医学系・理学系・生命工学系などの幅広い領域の多彩なテーマを学際的に取り扱っております。さらに近年では、農学分野における植物病理、水質浄化・土壌改良や発酵・応用微生物学、理工学分野におけるモデル生物学やゲノム疫学、バイオインフォマティクス、また、エクスポゾームなどの環境科学研究まで包括する多彩な領域における、最先端技術開発や新たな学術領域の開拓など、本学会が推進する研究フロンティアの裾野は加速度的に拡大しています。実際、これまで年1回開催される年次総会では、基礎生物学、生命科学、医学生物学の基礎から臨床における最新の話題のみならず、関連する領域も包含した多方面での最先端の学術研究成果が発表され活発に討論されることにより、関連分野の縦横断的で活発な学術交流がなされてきました。
第90回総会では、このような学術活動の成果と実績、および、本学会の極めて学際的な特色をさらに深化させるため「生命科学と細菌学の学術基盤と先端融合」のテーマのもとに、これまで異分野に幅広く展開してきた基礎細菌学の多彩な研究活動を糾合し、日本細菌学会のより一層の発展を図るものです。従いまして、本総会で発表される国内外の研究成果は、我が国にとどまらず世界に向けて発信されるものであり、その社会的また学術的意義と役割は極めて大きいものであると言えます。とくに、今回の総会では、シンポジウム企画調整委員会により策定された31のシンポジウムとともに、これまでにない企画として、一般演題(ポスター)に登録された演題のうち、 「生態(微生物叢:microbiota)」 「病原因子と病態」 「免疫・生体防御」 の3つの領域に応募された演題から、企画調整委員会により口頭発表の演題を選定して9つの「選抜ワークショップ」を開催いたします。さらに、MicrobiotaとInflammasome研究で世界の先導的な立場にある2名の研究者、Amrita Ahluwalia教授(英国ロンドン大学)とHasan Zaki教授(米国テキサス大学)を特別講演に招聘いたします。また、国内の演者としては、本学会名誉会員の前田 浩先生に、東北大学細菌学教室における化学療法研究の系譜・歴史を交えて教育講演をいただきます。さらに、海外研究者4名、国内研究者11名を招聘して企画する特別(教育)講演・国際シンポジウム(文部科学省新学術領域研究「酸素生物学」共催)、および、ICD講習会やランチョンセミナー(毎日1回)を開催して、会期を通して終始活発な学術交流の場を提供できるよう努める所存です(詳細は、本総会ホームページに掲載のプログラムをご覧ください)。
この度の総会では、400を超える一般演題をご登録いただきましたので、例年通り、沢山の優れた演題を、シンポジウム・ワークショップ・ポスターセッションにて多数ご発表いただきまして、活発な討論と情報交換がおこなわれるものと期待しているところです。 仙台では一昨年12月に地下鉄東西線が開業し、仙台駅から会場の仙台国際センターまでのアクセスが格段に良くなりました。日本細菌学会会員の皆さまにおかれましては、本学術集会に多数ご参加いただきますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。
| 第90回日本細菌学会 総会長 赤池 孝章 東北大学大学院医学系研究科教授 |
 |